ヨットクルージングサイト
カリブ海クルーズ
アンチヒーローシリーズ 西部劇アウトロー列伝
Part 1 全151回
いかにして西部劇狂になったか
ブッチ・キャサデイ

Part 2 全18回
怪盗P08
Part 3 全43回
ワイアット・アープ
Part 4 全82回
ビリー・ザ・キッド
Part 5 全146回
ジェシー・ジェイムス
創られた英雄
 地中海クルーズ
地中海クルーズメノルカ島の旅
エスパルマドール
カブレーラ島
ラタス島
イビザ北西部の島
サルジニア・アシナラ 島
エスベドラ島
サン・ミゲル村
プニョン・デ・イファク
フォルメンテーラ島
ドラゴネーラ
地中海孤島めぐり を終わって
ヨットのページへ
輸入代行のページへ
アンチヒーローシリーズ 西部劇アウトロー列伝
Part 1 全151回
いかにして西部劇狂になったか
ブッチ・キャサデイ

Part 2 全18回
怪盗P08
Part 3 全43回
ワイアット・アープ
Part 4 全82回
ビリー・ザ・キッド
Part 5 全146回
ジェシー・ジェイムス
創られた英雄
ヨットクルージングサイト
カリブ海クルーズ
アンチヒーローシリーズ 西部劇アウトロー列伝
Part 1 全151回
いかにして西部劇狂になったか
ブッチ・キャサデイ

Part 2 全18回
怪盗P08
Part 3 全43回
ワイアット・アープ
Part 4 全82回
ビリー・ザ・キッド
Part 5 全146回
ジェシー・ジェイムス
創られた英雄
 地中海クルーズ
地中海クルーズメノルカ島の旅
エスパルマドール
カブレーラ島
ラタス島
イビザ北西部の島
サルジニア・アシナラ 島
エスベドラ島
サン・ミゲル村
プニョン・デ・イファク
フォルメンテーラ島
ドラゴネーラ
地中海孤島めぐり を終わって
ヨットのページへ
輸入代行のページへ
アンチヒーローシリーズ 西部劇アウトロー列伝
Part 1 全151回
いかにして西部劇狂になったか
ブッチ・キャサデイ

Part 2 全18回
怪盗P08
Part 3 全43回
ワイアット・アープ
Part 4 全82回
ビリー・ザ・キッド
Part 5 全146回
ジェシー・ジェイムス
創られた英雄
ヨットクルージングサイト
カリブ海クルーズ
アンチヒーローシリーズ 西部劇アウトロー列伝
Part 1 全151回
いかにして西部劇狂になったか
ブッチ・キャサデイ

Part 2 全18回
怪盗P08
Part 3 全43回
ワイアット・アープ

Part 4 全82回
ビリー・ザ・キッド
Part 5 全146回
ジェシー・ジェイムス
創られた英雄
 地中海クルーズ
地中海クルーズメノルカ島の旅
エスパルマドール
カブレーラ島
ラタス島
イビザ北西部の島
サルジニア・アシナラ 島
エスベドラ島
サン・ミゲル村
プニョン・デ・イファク
フォルメンテーラ島
ドラゴネーラ
地中海孤島めぐり を終わって
ヨットのページへ
輸入代行のページへ
貿易風の吹く島から
|
|---|
| ヨットのクルージング関係の話題は http://gby.sblo.jp/ まで | ||||||||
 道産子。小学生の時、フランス人4人がヨットで世界1周する記録映画を見て、 人生の針路を決定する。水上生活者として20余年。前半は地中海、 後半はおもに大西洋とカリブ海で暮らす。 カリブの砂州、カージョ・オビスボにヨットを舫い棲家とする。(当時) 現在はコロラドの国立公園の山中に仙人のごとく暮らす。 のらり より転載しました。下記のウエブでカリブヨットクルーズを読むことができます。 著作権は作者とのらり編集部に属します。 カリブ海クルーズ 第1回 君よ知るや南の島 佐野 大西洋を渡る──地中海で数年クルーズした者にとっては当然とでもいうべき目標となる。地中海の、まるでバカンスの延長のようなセーリングに慣れてしまった自分とは対象的に、ときおりスペインのマリーナで出会う「カリブ帰り」たちは、本物の潮の香りを漂わせているように思えたものだった。 長いクルーズに出るときに一番苦心するのは、陸の上のシガラミを断ち切ることである。これさえいったんふっ切ってしまえば、あとは簡単だ。洋上を前進するしかないのだから。 私にとってのシガラミとは、かなり気に入っていたイビサ島での生活であり、大きく海側に開いたテラスを持つアパートであり、島の友人たちであり、それに本とレコードであった。当時、半年働くだけで残りの半年をセーリングすることが許される仕事を持ってはいたのだが、大洋を渡って向こう側で島巡りをするとなると、どうにも6カ月で足りるものではない。時間に追いまくられながらヨットで動くことほど愚かなことはない。そこで、地上のシガラミをスパッと切って…とはできずに、まるでキレの悪いナイフで押し切りするように、散々迷い悩んだ末に身の周りの物を友人宅に預け、いつの日かイビサ島に戻ってくる日の備えまで考えたりしながら、極めて思い切りの悪い状態で100パーセントの時間をセーリングにつぎ込むヨットライフに飛び込むことになった。結局それからイビサに戻ることはなく、10余年をカリブで過ごすことになったのだった。いま思えば、あのときの一大決心の重要な部分を占めていたのは「ケチの根性」であったような気がする。平たく言えば「どうせ生まれてきたのにやりたいことをやらずに老い朽ち果 てるのは損だ。体が動くうちにやりたことをやらなきゃ損だ」という、妙な人生損得理論が作用していたように思う。結婚して2年目の37歳の夏のことだった。 長い航海をするにあたって、海のベテランたちが膨大な量のアドバイスを書き残しているので、まずそれらを読破して、かれらの忠告に素直に従うのが最良の策と考えた。エンジンのスペアパーツにはじまり、緊急避難用の耐水広口ジェリーカンには釣り針、カンパン、薬、カロリーメイト、クラッカー、コンパス、ナイフ、水5リットル、反射鏡、発煙筒などなどを詰め込む。いざというときには、それらが即座に取り出せるようにコクピット近くに縛り付ける、などなど。しかし、先達の貴重な忠告どおりに準備などできるわけがないことを悟るまでにはそんなに時間はかからなかった。トテモじゃないが、何から何まで積み込むわけにはいかないのだ。エンジンのパーツを探しにでかけたときには、メカニックが言ったものである。「オイオイ、修理屋でも開く気か」 金にもスペースにも、ましてや積める重さにも絶対的な限度があるのだ。教科書どおりに備品やスペア、食料、医療品を積み込んだ日には、普通のヨットならば沈没することまちがいなしだった。安全を守るための備品の重さのせいで逆にヨットが危険な状態にさえなりかねなくて、ここでもまた切り捨て作業に迫られることになった。こんな風にして喫水線が20センチばかり余分に沈んだヨットで、不安と期待の入り混じった、奇妙な興奮に気を高ぶらせながら、一路カリブ目指してカナリー諸島のラスパルマスを離れたのである。よく晴れた冬の夕暮れどきのことだった。 我がヨット、アトランティスは1974年に建造された老朽船で、2本マストを持つ39フィートのケッチである。ヨット乗りは、とかく自分のヨットに対する思い入れが激しくて、自分の船が最高だと信じている。自分の船のことを説明するときに「決して速くはないが乗り心地が良い」とか「居住性が良い」というとき、それはセーリング性能が悪いということを意味している。「保針性がよい」は、舵の効きが悪くて狭い港内で苦労しているという意味だ。「波を叩かずに切るように走る」というのは、デッキが常に海水で洗われていて、いつでも水浸しになっているという意味である。とにかく誰もが自分のヨットが一番なのだ。「他人の女房の悪口は言っても、ヨットの悪口は言うな」という格言さえある。 そして我がヨット「アトランティス」のことである。少々コジツケがましいが、ヨットはライフスタイルであると言うのが私の持論である。私事として言えば、操船やメンテナンスでいったいどれだけ間違いを犯してきたことか。私のヨットはそうした私の数限りない、ときには大きなミステイクまで受け入れくれる船でなければならない。これまで何度「オット!」もしくは「アリャ!」を繰り返したことか。それでもどうにか目指す場所にたどり着いて人一倍セーリングを楽しめたのは、愛艇アトランティスが神経質なヨットではなく、下手な乗り手に寛容であったからだと思っている。性格的にアトランティスと私はウマが合ったのだろう。西部劇で馬の方が道を良く知っていて、持ち主のガンマンは馬の背で居眠りしているという図に似ていなくもない。 航海の途中、いったん貿易風のなかに入りそれなりにセールをセットしたあとは舵に全く触る必要もなく、私たちはアトランティスにただ運ばれている感じだった。こんな航海を20日間続けたあと、私たちは仏領マルチニク島に着いた。島を見逃してしまって半日ばかりの距離を通 り過ぎてから引き返すというアクシデントはあったけれども、これはアトランティスの罪ではない。 のらりのウエブマガジンに掲載されたカリブ海クルーズです。パートナーでもある佐野の39fのケッチ・アトランテイス号で大西洋を一緒に横断して、その後、夫妻によるカリブ海周航記です。全157回の初回をアップしました。リンクしましたのでご覧ください。 第1回から第101まで http://norari.net/carib/back_carib.php 第102回から第157まで http://norari.net/carib/back_carib02.php  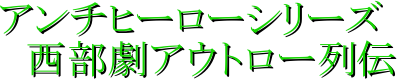 「のらり」より転載。著作権は佐野とのらり編集部に所属します。 Part 1 全151回 Part 2 全18回
のらりより転載。著作権は佐野とのらり編集部に所属します。 Part 5 全146回 ジェシー・ジェイムス 創られた英雄 全146回 佐野 Jesse Woodson James 第146回:ジェシー・ジェイムス〜創られた英雄 その146
エピローグ 《最終回》 初めてジェシー・ジェイムスの育ったカーニィーの農園を訪ねたのは、40年近くも前のことになろうか。家は崩れかかった丸太小屋にコロニアル風の木造2階建ての家を無理に繋げた小さなもので、畑の向こうに奴隷小屋が並んでいた。私たちのほかに訪問者はなく、地元の大学で歴史を専攻する学生が順に当番に当たっているだけだった。 その日はアメリカ南北戦争を専門にしている女学生が、寒そうにポツネンと居間の椅子に腰掛けて本を読んでいた。もちろん、入場料などなかった。まだ、カーニィーの町も、この観光資源を有効に生かそうとしていなかった。 30年経ってから、もう一度カーニィーを訪れて驚いた。広々とした駐車場に迎えられ、大きな博物館が隣接されていたのだ。そこで入場料を払い、ジェシーのピストルやライフル(だと伝えられているものだが)、ゼラルダやサムエルの大きなパネル、ジェイムス家とは関係のない、ただその当時のモノというだけの、家具や馬具が展示された狭い会場を回らなければ、オリジナルの家に入れないようになっていたのだ。もちろん、ゼラルダが目を剥くであろうほどバラエティーに富んだ土産物も売っていた。実際、ジェシー・バーガーにフランク・ビールがあっても驚かなかったことだろう。 家の周囲もアメリカの団地のようにきれいな芝生が広がり、ピクニックテーブルまでそこここに据え付けられている。崩れかかった丸太小屋はそうでもしなければ腐り果ててしまうのだろうか、真っ白に塗られ、丸太の間に詰め込むチンクと呼ぶ材料も、当時は泥、粘土に苔や草の根を混ぜたものだったのが、化学的なコーキング剤に変わっていた。ウィークデイだったのにもかかわらず、狭い家は人息れで蒸すほどの混みようだった。 ジェシー・ジェイムスは、母親のゼラルダが意図したように、地元の観光資源として立派な役割を果たしていた。それ以来、ジェシー・ジェイムスの家、農園を訪れたことがない。 西部劇受難の時代になってからも、ジェシー・ジェイムスの人気は衰えていない。最近、ブラッド・ピッツがジェシー・ジェイムスを演じ、プロデュースにも関わった映画『ジェシー・ジェイムスの暗殺』が造られている。原作はロン・ハンセン(Ron Hansen、原題は"TheAssassination ofJesse James by Coward RobertFord"と長ったらしい)、晩年のジェシー・ジェイムスとボブ・フォードに焦点を絞ったユニークな読み物になっている。 ジェシー・ジェイムス・ストーリーは、彼の生前からジョン・エドワーズが書き続けていたし、他にもパンフレットのような雑誌や薄手の本など、それこそゴマンと出版されていた。彼の死後も、ジェシー・ジェイムス・ブームは衰えることがなかった。それどころか、ハリウッドが野外にカメラを持ち出し、西部劇を製作し始め、ジェシー物を造り、ジェシーブームに輪をかけた。 アマチュアの数奇者とマジメな歴史家とが渾然となったアウトロー史で、ジェシー・ジェイムスほど書かれた人物はいない。出版物の数の多さは、他のアウトローたちをはるかに引き離し、断トツでトップだろう。 私が気楽に読み流すための、ハリウッド映画の延長のようなアウトローシリーズを書き始めた時、ブッチ・キャサディーやビリー・ザ・キッドと並んで、ジェシー・ジェイムスも当然脳裏に浮かんでいた。旅行のついでに、ジェシーに関係のあった場所に立ち寄り、写真を撮ったり、本を集めたりもしていた。だが、ジェシー・ジェイムスのことを知れば知るほど、彼の暗さ、陰湿な二重人格、変質狂的な殺人、エドワードに踊らされているだけなのに、それに気付かず増長していくエゴなど、嫌な面ばかりが鼻に付き、ジェシー・ジェイムスを取り上げることをためらわせた。 このような軽い読み物にしろ、伝記的要素をフンダンに持った話は、対象になる人物に程度の差こそあれ、惚れ込む要素がなければ耐えられない仕事になる。私にとって、ジェシーは憧れるところが全くない、無視してしまいたい存在だった。第一、ジェシーの生涯は西部劇のもつ大自然の雄大さ、砂塵の舞う辺境の町、ジョン・フォードが描くところのハリウッド映画的要素が全くないではないか。それに、ジェシーはカウボーイとして牛を追ったこともなく、ブロンコ(野生の馬)を乗りこなしたこともなく、バファローを撃ったこともないのだ。 一度でも殺戮に手を染めた者は、ましてやジェシーのように凄惨を極めた惨殺を繰り返してきた者には、生涯拭いきれない臭気が付きまとうのだろう。セントレリアの大量虐殺現場を訪れ、このシリーズには掲載しなかったが、北軍の負傷兵のペニスを切り取り、それを死者の口にくわえさせている写真を見た時、どのような人間がこんなことをするのだろう、そして、そんなことをした人間がそれからどんな生涯を送ったのだろう……という感慨に捉えられるのは私だけではあるまい。 しかし、こんな殺戮はアウシュヴィッツや日本軍の中国、満州侵略など、戦争に付き物だったのだろう。そして、そんなサディズムの極致のような殺しを行った男たちは、戦争が終わるとともに、隣りの親切なおじさんになり、店屋のオヤジになり、公務員や学校の先生に戻ったのだ。 すでに過ぎ去ったこと、現在の自分の存在とはおよそ無関係な史実を取り上げ、それを鳥瞰図的に眺め、批判するのは易しいことだ。私にしても、敗戦直後に生まれ、現在まで戦争を自分の身に降りかかる進行形で体験せずに済ましてこれたことを幸運だとするだけだ。 ジェシー・ジェイムスは16歳で南軍の下部組織に加わり、18歳のときに終戦を迎え、それからサディスティックな殺人鬼・チビのアーチの腰巾着として、ゲリラ集団・ブッシュワッカーになった。ジェシーを血で洗脳された南北戦争の犠牲者だったとすることはできない。南軍に参加した幾千幾万の若者は、それぞれの苦悩を抱えながらも敗戦を受け入れ、真っ当な戦後を迎えているのだ。 ジェシーは異常な戦争状態、戦後のゲリラ戦を殺されるまで続けたのだ。私はジェシーに犯罪者として、サディストとしての性格があり、そんな暗部がブッシュワッカー時代に深く広がって行ったのだと思う。彼は陰湿でご都合主義、自分本位の冷血な犯罪者だったと思う。 ジェシーが持っていたやりきれない暗さと欺瞞的性格が、私に彼を取り上げるのをためらわせた。しかし、アウトローシリーズと名付けた以上、ジェシー・ジェイムスを取り上げないわけにはいかない。 まず、驚いたのはジェシー・ジェイムスに関する出版物の多さだった。私が利用している地元の大学の図書館と町の図書館から、ザッと借り出しただけでも30〜40冊にはなるだろう。絶版になってから久しい本やパンフレットのたぐいはアマゾンを通して購入したり、他の大学の図書館からも郵送してもらった。 当然のことだが、すべてを読んだわけではない。最初の数ページに目を通しただけで、虚実混合で思い入れだけで書かれている西部冒険小説、南軍派、奴隷派のプロパガンダだと容易に嗅ぎ分けることができる。腐った卵は臭いを嗅ぐだけで分かるから、わざわざそれを食べてみる必要はない。 それほど沢山書かれているのだが、史実に基づいた本や調査レポートは限られている。 私の簡略化したアウトロー伝、ジェシー・ジェイムスを書く上でいつも卓上に置き参考にしたり、引用した主な本は以下の通りである。 The Rise and Fall of Jesse James by RobertLove Jesse James was My Neighbor by HomerCroy Jesse James was his Name by William A.Settler Jesse James "Last Rebel of the Civil War" by T. JStiles Frank and Jesse James by Ted P.Yeatman Jesse James and the Civil War in Missouri byRobert L. Dyer Inside War by Michael Fellman Quantrill and the Border Wars by William E.Connelly 他、John Newman Edward"Shelby and HisMen" 南北戦争関連の本は、リンカーンのものを含めると膨大な数が出ている上、その時代の地方史を加えると、まさに天文学的な数になるだろう。今でも、歴史専攻の大学生が好んで取り上げる時代の筆頭は南北戦争だ。 だが、このシリーズでは、南北戦争のことはジェシー・ジェイムスが関わった極めてローカルな事件のみに限った。 古い雑誌や新聞もインターネットで覗けるようになったので、とても重宝した。写真の多くはインターネットのサイトからの転載である。当然のことだが、インターネットから得られる情報は限られており、往々にして間違っている。手っ取り早く覗けるので便利だが…。 休日になれば、アウトローたちの足跡、主に墓探しに付き合わせた"卑怯な裏切り者"ボブ・フォードの末裔、かすかな血縁であるらしい私の連れ合い"フラカ"にありがとうと、この場を借りて言っておきます。とても本人に面と向かってはテレ臭くて言えないので。 のらりより転載。著作権は佐野とのらり編集部に所属します。
1-50 http://www.norari.net/outlaw_05/back_outlaw_JJ_01.php 51-100 http://www.norari.net/outlaw_05/back_outlaw_JJ_02.php 101 http://www.norari.net/outlaw_05/082814.php ここからは最終回146までは整理したものがないため順次次回をクリックしてください 2015-8-8  Part 4 全82回 ビリー・ザ・キッド 佐野 第1回:ビリー・ザ・キッド その1 全82回 130年目の恩赦? 西欧人はとかくやることが執念深い。諦めることを知らず、水に流すなんてもってのほかで、とりわけ、一度恨みをかうと何時までも覚えていて、機会あるごとにそれを思い起こさせようとする。 アメリカに住むようになってから初めて知ったことだが、"パールハーバー・デイ"というのが、未だに毎年のように大々的にマスコミに取り上げられるのにあきれた。パールハーバー襲撃の日(1941年12月7日)は、ワールドトレードセンタービル崩壊のテロ事件の日が"911"としてアメリカ人の記憶に焼き込まれたのと同様に、アメリカの歴史に永遠に刻まれることになるのだろう。 個人的な怨恨も何世代にも渡って尾を引く。それに政治的な色付けでもあろうものなら、大いに利用することにためらいはない。
ビリー・ザ・キッドは、ニューメキシコ(当時は領域)で死刑の判決を受け、縛り首になるのを待っていたところ、監視人二人を撃ち、脱獄逃亡し、執念のシェリフ、パット・ギャレットに撃ち殺された。ビリー・ザ・キッドがまだ獄中にあったとき、彼は当時の知事ルウー・ウォレスに恩赦を申請する手紙を書いている。この手紙は驚くほど綺麗な文字で、しかも正しい英語で書かれており、地方の大学で教鞭をとっている私の連れ合いに見せたところ、「私の生徒たちよりはるかに立派な英語だ」と嘆息したほどだ。
ビリーの恩赦請求に対し、ときの知事ルウー・ウォレスは1878年の殺害事件(リンカーン郡の戦争と言われている殺し合い)に関しては恩赦を約束したのだが、空約束で実行しなかった。もっとも、ビリー・ザ・キッドは他にもかなりの数の事件を巻き起こしてはいたのだが…。 それを、130年経った今頃になって、リチャードソン知事がたとえ大昔であろうと、一度知事たるものが約束したのなら、その約束を履行しなければならない、と言い出したのだ。 ビリーには直系の現存者がいるわけでなし、この恩赦は、ビル・リチャードソン知事の売名行為、スタンドプレイだとか、いや、ニューメキシコ州の観光(アウトローゆかりの村や町を訪れる観光客は多い)に大いに役立つとか言われ、ともかく話題になったことだけは確かだ。 だが、この恩赦に妙なところからクレームがついたのだ。ビリー・ザ・キッドを殺したシェリフのパット・ギャレットの孫だという男が、「それじゃ、うちの爺さんのパットの立場がなくなるじゃないか、恩赦になった人間を撃ち殺したことになるんだから」と、正式に裁判所に恩赦取り消しを要求したのだ。 いろいろな説があるにしろ、一般的にはパット・ギャレットは、ビリーがベッドで寝ているところを撃ち殺したと信じられており、"執念深い"上に"冷血"という評判がパット・ギャレットについて回ることになった。いくらなんでも寝込みを襲うのはフェアじゃないというわけだ。 その時ビリーが寝ていたのが、ペート・マックスウエルのベッドだったところから、殺されたのはペートで、ビリーは銃声を聞きつけ、まんまと逃亡し、今流に言えば、アイディンティティを変え、テキサスで平穏な生涯を過ごしたとか、負傷したがそのまま逃げおおせたとか、ヒーロー伝説に付き物の諸説が流れている。 現知事のビル・リチャードソンは、パット・ギャレットの末裔と面談することを約束したので、またマスコミの目を集めて会見の様子、内容が写真入りで報道されることだろう。 まだビリー・ザ・キッドの恩赦を発令するかどうかの裁定は下されていない。知事にとっては、これだけ話題になったのだから、それで十分というところだろう。 のらりより転載。著作権は佐野とのらり編集部に所属します。 Part 3 全43回 ワイアット・アープ 佐野
2015-11-23 |
||||||||
| |
| ロングクルージング関係の話題は http://gby.sblo.jp/ まで |
|---|
|
||||























